| ■適当講座■ |
| 10.花子で立体図 その他作図 |
| ☆半球立体の作図-補足2 |
| 補 足 1 補 足 2 | |
| 元図から半球立体図を作図しておきます。(図ota-201参照)。 |
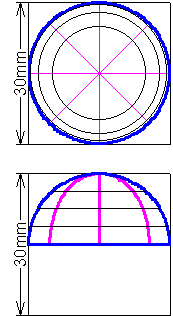 図ota-201 元図 |
| 出来上がった立体図をコピーして枠と底面の楕円を残し、他は削除します。(図ota-202参照)。 その後、楕円の中心に平面図の上面図の中心が垂直になるように配置します(図ota-202右)。 |
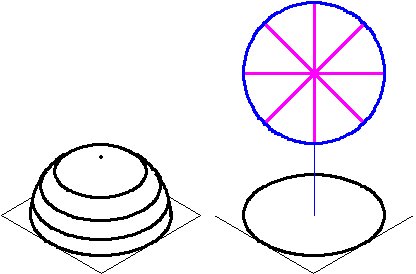 図ota-202 ピンク線を描くための準備 |
| 上面図のピンク線の端から楕円に向けて、垂直線を引きます(図ota-203左)。 引いた垂直線と楕円の弧(?)の交点から、対称方向の交点に線を引きます(図ota-203右)。 |
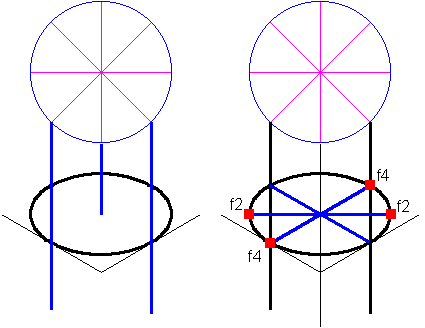 図ota-203 円を分割する線を楕円に複写 |
| 交点から交点の線が全部引けましたら、楕円ごとコピーしておきます。(図ota-204左)。 楕円と線の交点に点を打っておきます(図ota-204右)。 |
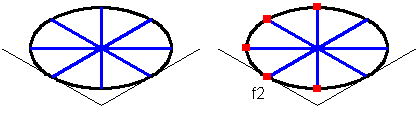 図ota-204 立体図に縦線を引く準備1 |
| 交点から交点に引いた線は削除して、底面から上に二番目の楕円 を高さを合わせて(図ota-205左)、コピーします(図ota-205右)。 |
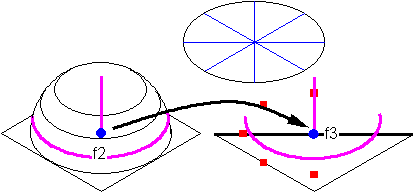 図ota-205 立体図に縦線を引く準備2 |
| コピーしておいた楕円+線の線をコピーした高さの合った楕円に中心を合わせて、
コピーします(図otb-206左)。 楕円と線の交点に点を打ちます(図otb-206右)。 |
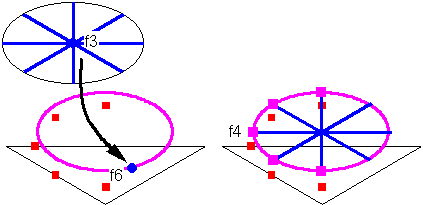 図ota-206 立体図に縦線を引く準備3 |
| 楕円と線を消します(図otb-207)。 |
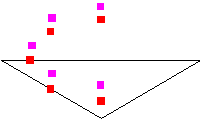 図ota-207 立体図に縦線を引く準備4 |
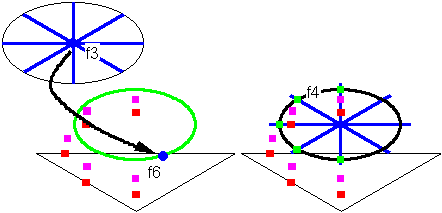 図ota-208 立体図に縦線を引く準備5/td> |
| 半球立体の下から3番目の楕円を高さが変わらないようにコピーします(図otb-209)。 |
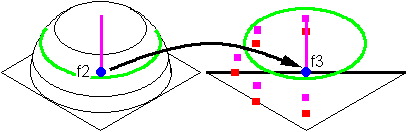 図ota-209 立体図に縦線を引く準備6 |
| 前にコピーしておいた楕円と線の線を立体図からコピーした
楕円の中心に合わせてコピーします(図otb-210左)。 楕円と線の交点に点を打ちます(図otb-210右)。 |
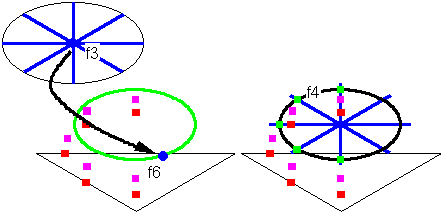 図ota-210 立体図に縦線を引く準備7 |
| 楕円と線を消します(図otb-210)。 |
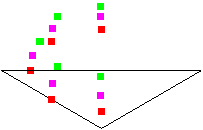 図ota-211 立体図に縦線を引く準備8 |
| 立体図の残りの楕円のコピーから点打ちまでも前述と同様に行います。(図otb-212〜otb-213)。 |
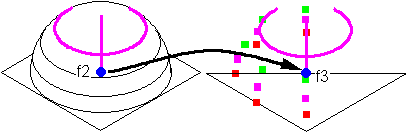 図ota-212 立体図に縦線を引く準備9 |
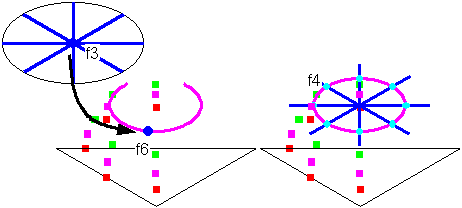 図ota-213 立体図に縦線を引く準備10 |
| 点を結ぶ場合、直線になるところは、簡単なので、後回しにして、曲線部分を先に描きます。 立体の高さ線を底面の中心に合わせます。 点の中心から高さ線の端点に適当にベジェ曲線を描きます。 この時、方向線を引っぱり出しておきます。 次に選択3(1図形変形?)でベジェ曲線を選択し、ベジェ曲線の全てのセグメントが、 全ての点の中心を通るように方向線で調整します(図ota-214)。 これを繰り返します。 |
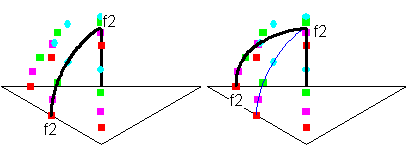 図ota-214 立体図に縦線(縦曲線?)を引く |
| 曲線が半面分引けたら、高さ線を対称に横方向で元図残すでミラーします(図ota-215左)。 その後、高さ線の端点を移動点として、曲線ごと、立体図の底面中心に移動します(図ota-215に右)。 |
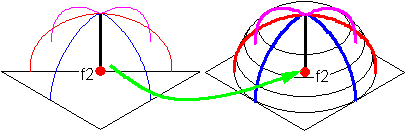 図ota-215 やっと合体した |
| 立体図の中に高さ線があれば消します。(図ota-216左)。 |
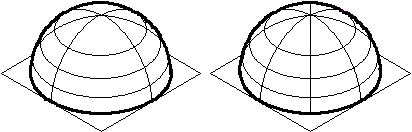 図ota-216 立体図の完成! お疲れさまでした |
| 補 足 1 補 足 2 | |
| ▲このページトップへ |
| Copyright(C) KinutaHandicraft |